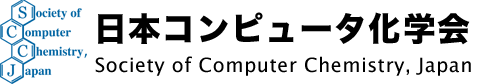NEWS | お知らせ
| 2025年 04月17日 【年 会】 | 2025年春季年会【プログラム公開のお知らせ】 2025年春季年会のプログラムを公開しました。発表者の方は発表番号を確認の上、要旨の作成をお願いします。 |
| 2025年 02月21日 【年 会】 | 2025年春季年会【受付開始のお知らせ】 2025年春季年会の各種申し込み受付を開始しました。 |
| 2024年 12月15日 【年 会】 | 2025年春季年会【開催日決定のお知らせ】 2025年の春季年会は、6月5日(木)〜6月6日(金)の2日間で開催します。 各種受付の開始は2月下旬を予定しています。詳細は年会のページをご確認ください。 |
| 2024年 08月07日 【年 会】 | 2024年秋季年会(サイト更新)のお知らせ 2024年秋季年会のWebページが新しくなりました。 各種申し込みが開始されています。 |
| 2024年 06月06日 【年 会】 | 2024春季年会【要旨と予稿集】 2024春期年会の参加者の皆様は、年会プログラムページから発表の要旨と予稿集にアクセスできます。 参加者宛に事前通知されたアカウントとパスワードにてアクセスお願いします。 |
Foreword from SCCJ
「コンピュータ化学によるヒューマンプロテクトの実現」を特集するにあたって
豊橋技術科学大学 船津 公人
環境問題、エネルギー資源問題、食糧問題といった地球規模の課題とともに、わが国においては急速に高齢化社会への対応が求められている。また、国民の意識、価値観は物質的な面から精神的な豊かさを重視する方向に変化しており、潤いのある社会の構築が求められている。「成長」をキーワードにしてすすんできた文明から、「質を重んじる社会」、「価値の創造を価値とする社会」へと文明を転換することが必至となっている。限られた資源、エネルギー、空間の中で人と人、自然と人の共生の論理と倫理に裏打ちされた科学技術システムと社会システムの構築が急務であり、「持続可能な社会」への展望を開く科学技術の果たす役割はますます大きくなっている。物質科学分野においては高度情報化社会を支える高機能性材料(ナノ機能性物質、触媒)の設計、それを創製する技術、人間・環境調和型分析技術および高効率生産プロセス技術の開発、そしてポストゲノムとして生体関連機能物質の解析・設計および創製などが強く求められている。数値実験、コンピュータ・シミュレーション、そして化学・生体関連知識情報処理統合的な活用は、社会的な要請であるこれらの課題にとって不可欠な技術であり、実験先導型から予測先導型へのパラダイム転換と併せてその重要性はますます大きくなっている。これらを強力に支援する分野横断的な研究展開が急務となっている。グリーンケミストリーを志向した環境負荷の低減を実現する機能性分子・材料レベルから物質・エネルギー循環に関わる地域環境情報システム構築に至る異次元間のミクロからマクロまでの包括的かつ学際的なコンピュータ科学技術および情報基盤の構築とその展開が求められている。本特集では、この思想につながる研究に取り組んでいる方々からご投稿頂いた論文を通常と同じ審査システムを経て掲載するものである。
▼